電通CMクリエイター 見市沖のこれからのCMの話をしよう【大瀧 篤氏/諸星 智也氏】
AIを知ることは 人間の心を知ること
電通のCMクリエイター・見市沖氏が広告制作の最前線で活躍するクリエイターと、これからのCMの在り方を探る連載企画の第8回。今回の対談相手はPARCO『グランバザール』、KDDI「au」の広告キャンペーンなど、幅広い領域でAIを活用したプロジェクトを手掛ける大瀧篤氏と諸星智也氏。広告クリエイティブとAIをテーマに、心を動かすためのAIとの向き合い方や、AI活用の可能性について語っていただいた。(取材:2024年10月30日)
【 CM INDEX 2025年1月号に掲載された記事をご紹介します。所属役職は当時のものです。】
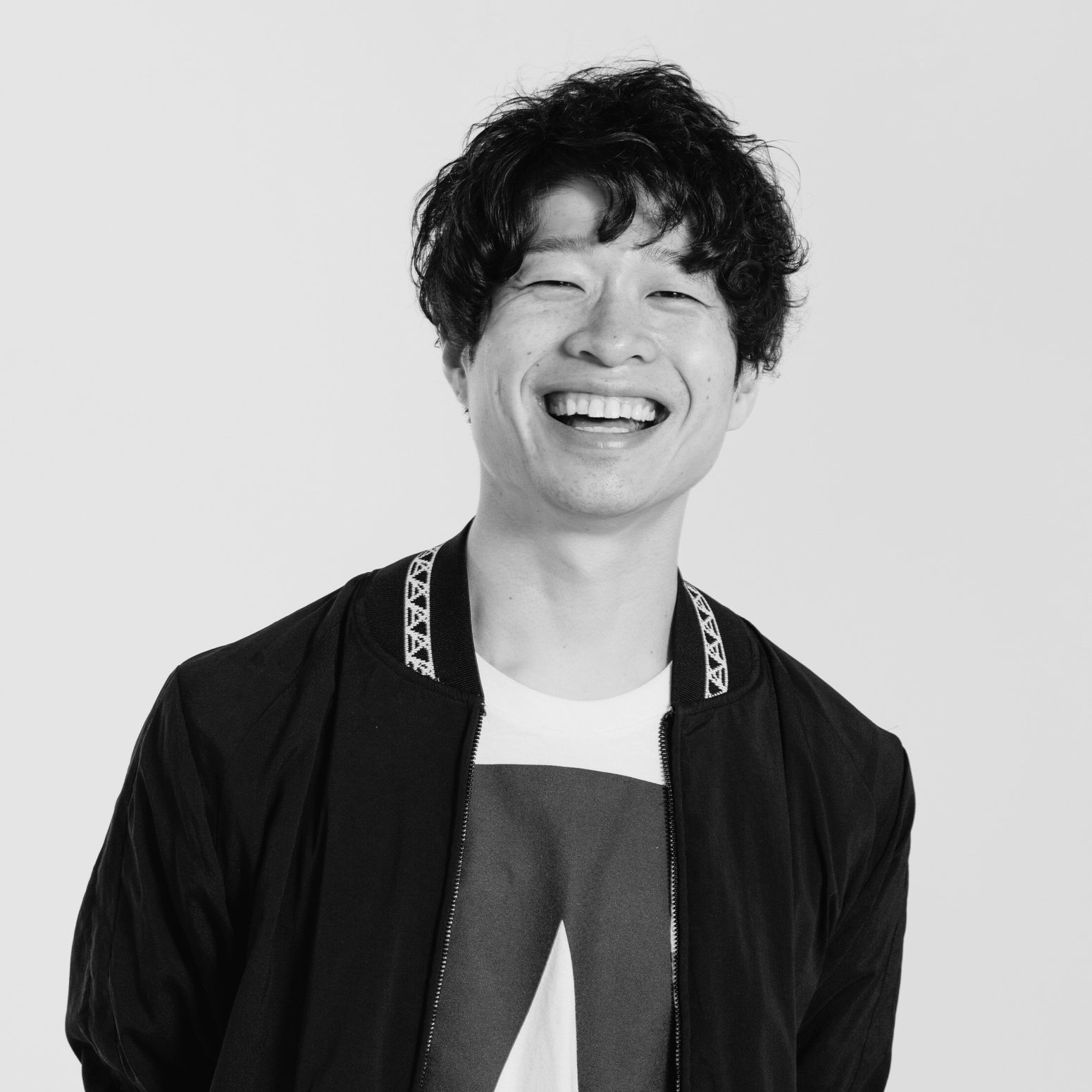
大瀧 篤氏
株式会社 電通 zero/Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブディレクター/クリエイティブテクノロジスト
大学・大学院でAIの研究と小型衛星開発に取り組み、2011年電通入社。リアル体験×テクノロジーのクリエイティブを武器に、企業・国家事業のソリューションやR&Dプロジェクトに関わる。Cannes Lions、One Show、Clioをはじめ、ACCや文化庁メディア芸術祭など国内外で100以上の受賞。著書に『クリ活2−クリエイターの就活本:デジタルクリエイティブ編』。世界ゆるスポーツ協会 理事/スポーツクリエイター
株式会社 電通 zero/Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブディレクター/クリエイティブテクノロジスト
大学・大学院でAIの研究と小型衛星開発に取り組み、2011年電通入社。リアル体験×テクノロジーのクリエイティブを武器に、企業・国家事業のソリューションやR&Dプロジェクトに関わる。Cannes Lions、One Show、Clioをはじめ、ACCや文化庁メディア芸術祭など国内外で100以上の受賞。著書に『クリ活2−クリエイターの就活本:デジタルクリエイティブ編』。世界ゆるスポーツ協会 理事/スポーツクリエイター
諸星 智也氏
株式会社 電通
クリエイティブテクノロジスト/プランナー
筑波大学大学院エンタテインメントコンピューティング研究室修了。電通入社後はテクノロジーを起点とした企画・演出などを得意とし、クリエイティブテクノロジストとして映像・空間・デジタル・XRなど手法にとらわれないさまざまな案件を担当。文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業採択。受賞歴はCICLOPE Asia Winner、Technical Direction Awards Silver、朝日広告賞、準朝日広告賞、Cresta Awards bronzeなど
株式会社 電通
クリエイティブテクノロジスト/プランナー
筑波大学大学院エンタテインメントコンピューティング研究室修了。電通入社後はテクノロジーを起点とした企画・演出などを得意とし、クリエイティブテクノロジストとして映像・空間・デジタル・XRなど手法にとらわれないさまざまな案件を担当。文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業採択。受賞歴はCICLOPE Asia Winner、Technical Direction Awards Silver、朝日広告賞、準朝日広告賞、Cresta Awards bronzeなど

見市沖氏
株式会社 電通 zero
クリエーティブ・ディレクター/コピーライター/CMプランナー
2006年電通入社。近作は、でで出前館、ポケモン愛と自由、タイムツリーはじめました、ポッキー、パズドラ。TCC新人賞、ACC賞、国際PRゴールデンアワードなど受賞。出前館は2021年度作品別CM好感度1位。
株式会社 電通 zero
クリエーティブ・ディレクター/コピーライター/CMプランナー
2006年電通入社。近作は、でで出前館、ポケモン愛と自由、タイムツリーはじめました、ポッキー、パズドラ。TCC新人賞、ACC賞、国際PRゴールデンアワードなど受賞。出前館は2021年度作品別CM好感度1位。
幅広い領域でAIなどのテクノロジーと体験を掛け合わせた企画を手掛ける
見市:これからの広告クリエイティブとAIをテーマに話していきたいと思います。まずクリエイティブテクノロジストであるおふたりの仕事について、聞かせていただけますか。
大瀧:テクノロジーを用いた広告キャンペーンや商品開発、R&D、ライブ演出など幅広い領域で活動しています。なかでもリアルな体験とテクノロジーを掛け合わせた企画を得意としています。最近話題になったのは松平健さんを3Dデータ化したPARCO『グランバザール』の「マツケンARパレード」※1でしょうか。諸星くんと担当した仕事で、松平さんが店頭に浮かび上がるAR施策やCMを展開しました。AIを主軸とした企画では、伊藤忠商事『きみとAIの!?な未来旅行展』があります。未来に関する論文や研究データをAIに学習させ、“あるかもしれない未来”を体験できる仕掛けをAIで制作したイベントです。
諸星:クリエイティブテクノロジストとプランナーを兼任しているので企画から考えるケースも多いですし、テクノロジーから逆算して企画することもあります。昨年のKDDI『au』の年始CMは後者で、生成AIと「三太郎」CMを掛け合わせたいというご相談から生まれたものです。このほか最近の仕事ではモトローラ・モビリティ・ジャパンのスマホ『motorola razr 50』のCMも担当しました。CMに登場するアバターの声は、AIが学習したタレントの声を子どもの声に変換したものです。
見市:MVやライブの演出なども手掛けていますよね。
諸星:MV制作は趣味の延長線でもあるのですが、そこで生成AIなどの実験を行って、そのチャレンジで得た知見をクライアントワークに生かすことも多いですね。
見市:ありがとうございます。最近、AIを使った広告が目立つようになりましたが、心を動かすという意味でAIはうまく力を発揮できていると感じますか。
大瀧:テクノロジーを用いた広告キャンペーンや商品開発、R&D、ライブ演出など幅広い領域で活動しています。なかでもリアルな体験とテクノロジーを掛け合わせた企画を得意としています。最近話題になったのは松平健さんを3Dデータ化したPARCO『グランバザール』の「マツケンARパレード」※1でしょうか。諸星くんと担当した仕事で、松平さんが店頭に浮かび上がるAR施策やCMを展開しました。AIを主軸とした企画では、伊藤忠商事『きみとAIの!?な未来旅行展』があります。未来に関する論文や研究データをAIに学習させ、“あるかもしれない未来”を体験できる仕掛けをAIで制作したイベントです。
諸星:クリエイティブテクノロジストとプランナーを兼任しているので企画から考えるケースも多いですし、テクノロジーから逆算して企画することもあります。昨年のKDDI『au』の年始CMは後者で、生成AIと「三太郎」CMを掛け合わせたいというご相談から生まれたものです。このほか最近の仕事ではモトローラ・モビリティ・ジャパンのスマホ『motorola razr 50』のCMも担当しました。CMに登場するアバターの声は、AIが学習したタレントの声を子どもの声に変換したものです。
見市:MVやライブの演出なども手掛けていますよね。
諸星:MV制作は趣味の延長線でもあるのですが、そこで生成AIなどの実験を行って、そのチャレンジで得た知見をクライアントワークに生かすことも多いですね。
見市:ありがとうございます。最近、AIを使った広告が目立つようになりましたが、心を動かすという意味でAIはうまく力を発揮できていると感じますか。
※1.2024年1月開催のPARCO『グランバザール』に合わせて、ARアプリを用いて3Dデータ化された松平健が全国の店舗に1日限定で出現する “マツケンARパレード”や、InstagramのARフィルター、その世界観を描くCMなどを展開。
AIで心を動かすことは大きな課題中長期的な研究開発にヒント
諸星:それは自分にとっても大きな課題です。ここ1年で「AIを使って何かやりたい」というご相談が増えているのですが、効率化の部分でAIを使用することが多いんですね。感情に訴えるという点では、すべて人間の手で制作する方がいい場合も少なくありません。
大瀧:常に新しい文化を発信しているPARCOや、ユーモラスな広告が得意なキンチョールといった企業・ブランドの人格に合ったAIの使い方をしている広告はチャーミングに見えますよね。一方でAIを使う必要性が分かりにくい広告表現も見受けられます。その企業やブランドが「好き」といった気持ちを作りたいときに、あえてAIという要素を入れる必要はないと思っています。
見市:文脈を理解した上でAIにトライするのは意味があるけれど、AI活用が目的になっている場合もありますね。
大瀧:ブランディングとして継続的にテクノロジーの活用を積み重ねていくのであれば、素晴らしいと思います。
見市:バーチャルタレントなども目にしますが、感情のないキャラクターに共感するのは難しいので、長期的にイメージ構築することで、愛は貯まっていくのだと思います。AIやテクノロジーを使った印象的な事例はありますか。
諸星:過去のデータや事例をAIに学習させ、それを元に新しいプロダクトや価値を中長期的に研究開発していく。そうしたデータビジュアライズのような取り組みがエモーションを動かすのではと考えています。そういう意味では、ソニーコンピュータサイエンス研究所が手掛けている京都の西陣織をAIで未来につなげるというプロジェクトに注目しています。職人さんが減っている中、AIに西陣織のテキスタイルを学ばせて工房と一緒に新たなデザインを生み出すといった活動で、広告業界でもこうした社会的意義がある取り組みをもっと作っていきたいと感じています。
大瀧:常に新しい文化を発信しているPARCOや、ユーモラスな広告が得意なキンチョールといった企業・ブランドの人格に合ったAIの使い方をしている広告はチャーミングに見えますよね。一方でAIを使う必要性が分かりにくい広告表現も見受けられます。その企業やブランドが「好き」といった気持ちを作りたいときに、あえてAIという要素を入れる必要はないと思っています。
見市:文脈を理解した上でAIにトライするのは意味があるけれど、AI活用が目的になっている場合もありますね。
大瀧:ブランディングとして継続的にテクノロジーの活用を積み重ねていくのであれば、素晴らしいと思います。
見市:バーチャルタレントなども目にしますが、感情のないキャラクターに共感するのは難しいので、長期的にイメージ構築することで、愛は貯まっていくのだと思います。AIやテクノロジーを使った印象的な事例はありますか。
諸星:過去のデータや事例をAIに学習させ、それを元に新しいプロダクトや価値を中長期的に研究開発していく。そうしたデータビジュアライズのような取り組みがエモーションを動かすのではと考えています。そういう意味では、ソニーコンピュータサイエンス研究所が手掛けている京都の西陣織をAIで未来につなげるというプロジェクトに注目しています。職人さんが減っている中、AIに西陣織のテキスタイルを学ばせて工房と一緒に新たなデザインを生み出すといった活動で、広告業界でもこうした社会的意義がある取り組みをもっと作っていきたいと感じています。
無機質なデータの裏側にあるストーリーをAIで可視化する
大瀧:日本酒でも同じような例がありますね。こういう場合、職人さんの頭と手にしか存在しない経験知のようなものを言語化して、AIにインプットすることが必要なのですが、このプロセスに大きな意味がある。これまでブラックボックスになっていた知識やノウハウが明文化されることは、その文化が次世代に受け継がれる可能性が高まるということですから。広告の例では、アイルトン・セナの走行記録を光と音で再現した『Sound of Honda/Ayrton Senna 1989』※2はひとつのヒントになると思います。無機質なデータには何も感じませんが、その裏にあるエモさや意味をAIを使って映像やグラフィックといった目に見える形に変換すると心を動かすことができる。データ解析する過程やデータそのものに感情を揺さぶるストーリーがあると、そのプロジェクトや作品に深みが生まれ、それを見た人が誰かに話したくなる。長い目で見ると、人間がハッピーになるきっかけにもなりうると思います。
見市:AIによるコピーライティングをどうお考えでしょうか。
大瀧:おふたりもご存じの通り、電通には私も開発に関わった『AICO』※3という広告コピー生成システムがあります。2015年後半から開発をスタートした初代AICOは“新入社員”のようだと思いました。完璧な答えは出てこないけれど、自分にない視点やインスピレーションを与えてくれる存在。現在は『AICO2』に進化して量だけでなくコピーとしての質も向上しています。コピーライターの思考プロセス自体を学習するなどブラッシュアップを続けているので、長期的にはそのまま使えるコピーを出してくる可能性はあると思います。
見市:人間のコピーライターが不要になるのでしょうか。
大瀧:多少役割や必要なスキルは変わるかも知れませんが、今後も必要な人材です。AIにコピーを書かせるにも最後は採用するコピーへの判断が必要ですし、コピーを考えてもらうディレクションは必ず人間がするので。それはコピーライティングをしてきた人が当然上手です。一方でAIに任せられるパートも増える分、“言葉のプロ”として活躍する業務領域がより拡張するようにも思います。
見市:AIによるコピーライティングをどうお考えでしょうか。
大瀧:おふたりもご存じの通り、電通には私も開発に関わった『AICO』※3という広告コピー生成システムがあります。2015年後半から開発をスタートした初代AICOは“新入社員”のようだと思いました。完璧な答えは出てこないけれど、自分にない視点やインスピレーションを与えてくれる存在。現在は『AICO2』に進化して量だけでなくコピーとしての質も向上しています。コピーライターの思考プロセス自体を学習するなどブラッシュアップを続けているので、長期的にはそのまま使えるコピーを出してくる可能性はあると思います。
見市:人間のコピーライターが不要になるのでしょうか。
大瀧:多少役割や必要なスキルは変わるかも知れませんが、今後も必要な人材です。AIにコピーを書かせるにも最後は採用するコピーへの判断が必要ですし、コピーを考えてもらうディレクションは必ず人間がするので。それはコピーライティングをしてきた人が当然上手です。一方でAIに任せられるパートも増える分、“言葉のプロ”として活躍する業務領域がより拡張するようにも思います。
※2. 故アイルトン・セナが1989年のF1日本グランプリ予選で樹立した世界最速ラップ(当時)の軌跡を、エンジン音とコース上に設置したLEDライトで再現したプロジェクト。2014年に公開され国内外で多数の広告賞を受賞した。
※3. 電通がAIによる広告コピー生成システム『AICO2』を2024年8月に公開。心を動かすコピーを生み出すための推論能力を高めるべく、電通のコピーライターが長年培ってきた創造的思考モデルなどを学習させたという。
※3. 電通がAIによる広告コピー生成システム『AICO2』を2024年8月に公開。心を動かすコピーを生み出すための推論能力を高めるべく、電通のコピーライターが長年培ってきた創造的思考モデルなどを学習させたという。
AIが不得手なことは“解釈” データを読み解くのは人間の仕事
見市:広告クリエイティブにおいて、AIが得意なこと、苦手なことを挙げるとしたら、どのようなことでしょうか。
大瀧:得意なのは“量を出せる”ことです。最初から正解がでてくることはありませんが、大量に生成されるアイデアに向き合って「これは違う」「ここはまあまあ」などと対話を繰り返す中で、自己分析を進めることには役立ちます。量に加えて情報処理の速度も上がっているので、対話スピードも増しています。不得手な分野は“倫理観”です。法律や人間の意識が変容し続ける中で、一つひとつの倫理観を言語化してプログラミングすることは不可能に近いので、そこは人間が介在しないと難しい領域ですね。
諸星:僕は画像生成をしながら企画を考えることが多いので、イメージの視覚化に使えると思います。言語化したアイデアがビジュアルに定着しないときなど、思考の整理に活用しています。苦手なことはアートやストーリーの“解釈”です。渋谷で高校生がジャンプしている画像があったとして、人間だったら過去の経験や情報を元に解釈しますが、それがAIにはできない。大量の案は出せても倫理感を含めた読み解き方は人が教える必要があるんですよね。
大瀧:得意なのは“量を出せる”ことです。最初から正解がでてくることはありませんが、大量に生成されるアイデアに向き合って「これは違う」「ここはまあまあ」などと対話を繰り返す中で、自己分析を進めることには役立ちます。量に加えて情報処理の速度も上がっているので、対話スピードも増しています。不得手な分野は“倫理観”です。法律や人間の意識が変容し続ける中で、一つひとつの倫理観を言語化してプログラミングすることは不可能に近いので、そこは人間が介在しないと難しい領域ですね。
諸星:僕は画像生成をしながら企画を考えることが多いので、イメージの視覚化に使えると思います。言語化したアイデアがビジュアルに定着しないときなど、思考の整理に活用しています。苦手なことはアートやストーリーの“解釈”です。渋谷で高校生がジャンプしている画像があったとして、人間だったら過去の経験や情報を元に解釈しますが、それがAIにはできない。大量の案は出せても倫理感を含めた読み解き方は人が教える必要があるんですよね。
広告業界のプラットフォーム側にもAI活用による業務効率化の視点を
見市:これからの広告業界において、AIの使い方はどのように変化すると考えますか。
諸星:AIはもっと敷居が下がって高度化すると思うので、Photoshopのように“ツール化”していくのではないでしょうか。そうした誰もが気軽に使えるAIと、よりハイコンテクストで専門的なデータを扱うAIに二極化していくのではと想像しています。あとはAIについて知識や興味がない僕の両親のような人が見ても、十分に楽しめてあっと驚くような広告を作っていかなくてはという思いもあります。
大瀧:業界の体質改善という意味で、制作現場のプラットフォーム側にAIを用いることを提案したいです。ゲームの世界でよく使われているのですが、空間をAIで管理するという“空間AI”という考え方が業務効率化に役立つと思います。例えば撮影スタジオの管理やタイムキーピングをAIに任せてみたら、大幅な時間短縮ができるのではないでしょうか。撮影前にAIを使ってライティングの位置といった不確定要素を高い精度で減らし、その知識を蓄積・共有できるスタジオがあれば、大きなアドバンテージになる。これまではより良いものを作るにはどんなに時間をかけてもいいと思っていましたが、最近娘が生まれたことで考え方が変わりました。どのポジションの人も健全に働ける環境を作ることが質の高い広告作りにつながるはずです。
見市:今後、個人として挑戦したいことはありますか。
諸星:テクノロジーの開発には時間がかかるため、表現技術の研究開発からスタートできるような中長期的なプロジェクトに取り組んでいきたいと思っています。
大瀧:私も長いスパンをかけて実験をしながら、その企業だからこそ意味のあるAI活用をすることが理想だと考えます。『AICO』でいえば、コピーライティングに知見と実績がある電通が作ったからこそ意味がある。AI活用が当たり前になるからこそ、流行りだからではなく企業や商品のDNAを反映させたブランディングにAIを使うといったチャレンジをしたいですね。長期的なパートナーとして、その企業ならではのAIツールを作るところからご一緒できたら、より本質的な成果を生むことができると思います。
諸星:AIはもっと敷居が下がって高度化すると思うので、Photoshopのように“ツール化”していくのではないでしょうか。そうした誰もが気軽に使えるAIと、よりハイコンテクストで専門的なデータを扱うAIに二極化していくのではと想像しています。あとはAIについて知識や興味がない僕の両親のような人が見ても、十分に楽しめてあっと驚くような広告を作っていかなくてはという思いもあります。
大瀧:業界の体質改善という意味で、制作現場のプラットフォーム側にAIを用いることを提案したいです。ゲームの世界でよく使われているのですが、空間をAIで管理するという“空間AI”という考え方が業務効率化に役立つと思います。例えば撮影スタジオの管理やタイムキーピングをAIに任せてみたら、大幅な時間短縮ができるのではないでしょうか。撮影前にAIを使ってライティングの位置といった不確定要素を高い精度で減らし、その知識を蓄積・共有できるスタジオがあれば、大きなアドバンテージになる。これまではより良いものを作るにはどんなに時間をかけてもいいと思っていましたが、最近娘が生まれたことで考え方が変わりました。どのポジションの人も健全に働ける環境を作ることが質の高い広告作りにつながるはずです。
見市:今後、個人として挑戦したいことはありますか。
諸星:テクノロジーの開発には時間がかかるため、表現技術の研究開発からスタートできるような中長期的なプロジェクトに取り組んでいきたいと思っています。
大瀧:私も長いスパンをかけて実験をしながら、その企業だからこそ意味のあるAI活用をすることが理想だと考えます。『AICO』でいえば、コピーライティングに知見と実績がある電通が作ったからこそ意味がある。AI活用が当たり前になるからこそ、流行りだからではなく企業や商品のDNAを反映させたブランディングにAIを使うといったチャレンジをしたいですね。長期的なパートナーとして、その企業ならではのAIツールを作るところからご一緒できたら、より本質的な成果を生むことができると思います。
“人間考察のプロ”である広告業界の人は本質的にAI向き
見市:これまでのお話を通して、AIは人間らしさや企業の個性を引き出すことができるとあらためて気付きました。
大瀧:「AIを知る=人間を知る」ことだと思います。そもそもAIというのは人間を模擬しようとしている。そんなAIに向き合っていくと「人間にしかできないこととは」「そもそも人間ってなんだろう」という問いに必ずぶつかります。AIと向き合うほど人間の仕組みを知りたくなる。実際、私は大学・大学院でAIを専門に研究していましたが、人間の気持ちって面白いなと思って電通の門を叩いた人間ですから。人間の気持ちを考えるのが広告の仕事ですので、広告業界の方々は本質的にAIに向いていると思います。「AIに仕事を奪われる」といった意識ではなく、“人間考察のプロ”として人間と向き合うという気持ちでAIに触れてみると、新たな視座を得られるのではないでしょうか。
大瀧:「AIを知る=人間を知る」ことだと思います。そもそもAIというのは人間を模擬しようとしている。そんなAIに向き合っていくと「人間にしかできないこととは」「そもそも人間ってなんだろう」という問いに必ずぶつかります。AIと向き合うほど人間の仕組みを知りたくなる。実際、私は大学・大学院でAIを専門に研究していましたが、人間の気持ちって面白いなと思って電通の門を叩いた人間ですから。人間の気持ちを考えるのが広告の仕事ですので、広告業界の方々は本質的にAIに向いていると思います。「AIに仕事を奪われる」といった意識ではなく、“人間考察のプロ”として人間と向き合うという気持ちでAIに触れてみると、新たな視座を得られるのではないでしょうか。
文:是澤励
その月のCM業界の動きをデータとともに紹介する専門誌です。



